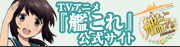氷の国の王子様 第1巻 小野ハルカ
小野ハルカ氏著の、華麗なるアイスホッケー物語、「氷の国の王子様」 の第1巻です。
掲載誌は 「少年サンデーS」。
【収録話】
| 第1ピリオド : 「王子の降臨」 | 第3ピリオド : 「王威発揚」 | 第5ピリオド : 「王子の出征」 |
| 第2ピリオド : 「勅旨」 | 第4ピリオド : 「女王の棺」 |
舞台は北海道氷人町 (架空) の 「私立聖堂騎士学園」。昨年全国大会で準優勝している、アイスホッケーの名門校。
主人公は、ホッケーの本場カナダ (氷の国) から、この学園に転校して来た天才プレイヤー、北大路アーサー (王子様)。
常に光輝く背景を背負って登場し、絶対的な自信と人を見下すことに慣れきった性格で、自らを “王子様” と自称する。
しかし、自信に見合うだけの裏づけと実力を持ち合わせており、アーサーの持つ野望は大胆かつ壮大なものでした。
天才プレイヤーが弱小チームを救う、といったストーリーではなく、強豪チームを主人公が自らの野望達成のために利用する
というところが面白いですね。まぁ、短期連載予定とのことなので、下のレベルからちまちまレベルアップしてられないってのも
あるんでしょうけど。それと、アーサーの性格をコミカルに描いて、嫌味に感じさせないところは上手いと思います。
自宅のスポーツ用品店でアーサーと出会ったホッケー部の少年、城山咲人。高い “空間把握能力” を持ちながら、その能力を
活かしきれていない、アーサーの王子様発言へのツッコミ役。ホッケー部の中では一番 “伸び代” がありそうなので、成長物語
として考えれば、サキが一番主人公っぽい立ち位置に居ます。でも、主人公になるにはちょっと地味すぎるかな。
同じくホッケー部にして、サキの幼馴染の堀川花。高いハンドリング能力を持つ、ホッケー部のレギュラー。ツーサイドアップの
髪型で、太い眉毛と普段は閉じている目が特徴。基本的にのんびりしていて、物事に動じない性格っぽい。目を開くと覚醒する
などの設定は特に無さそうですが、試合中に目を開く時は、少し意地が悪そうになるところが可愛いです。
いや、目を閉じてても可愛いんですけどね。ハナは好きです (笑)。
まぁ、最初は何で女子選手が一緒に混じってるのかとも思ったんですが、フィクションとして華やかさを演出するには、可愛い
女の子の一人でも居た方が良い気はします。努力と根性で全国を勝ち上がっていく、熱血スポ根漫画ならともかく、このくらい
コメディ寄りでライトな漫画なら、それもアリかな、と。
聖堂騎士学園アイスホッケー部レギュラー選手の残りは、キャプテンの近衛正治郎、ディフェンダーの庭園雪彦と櫓勝高。
近衛は全国一のセーブ率を誇る、鉄壁のゴールキーパー。ディフェンスの二人も能力が高く、去年の全国大会ではこの三人で
守りまくって、何とか準優勝をもぎとったという結果だったらしいです。
近衛がいきなりサキに鉄拳を食らわせた時は、ハナと一緒に 「えー…」 と眉を顰めましたが、これはそのあと自分の間違いに
気づいて、土下座するような極端な性格を強調するためだったのかな。他の二人も、近衛と一緒になって正座に三つ指ついて
アーサーを勧誘に来るなど、礼儀正しいを通り越した極端な性格のようですが、今回はあまり活躍の場はありませんでした。
一応三人とも中学三年ということですが、櫓はヒゲまで生やして高校三年と言っても通用しそうな見た目ですし、サキ、ハナ、
アーサーの三人が幼く見えるのと相まって、チーム内のギャップがかなりあります。
そして監督は、ホッケー大国ロシアで、ジュニアチームを全国制覇に導いたという、シスターソフィア。前の監督は、成績不振を
理由にクビにした…って、中学の部活の監督を結果でクビにするとか、結構凄いですね (笑)。
シスターは、脳のリミッターを外すことで、人並外れた洞察力と記憶力を得たのと引き換えに、身体と脳に負担をかけて命を
縮める危険を抱えるという、ハイリスクな能力の持ち主。棺桶持参で登場するコーチ (監督) とか、どこのミスター・ミラクルだ
ってツッコミを入れると、古すぎて誰もわからない可能性があるのでやめときます (もう遅い)。
アイスホッケーのルールは全然知りませんが、基本的にはスティックを使ってパックをゴールに入れるということだと思うので、
それほど難しく考えることなく読めると思います。特殊なルールについては、作中でちょこちょこ説明してくれてますし。
マイナーなスポーツの漫画とか好きですし、ハナもシスターも可愛いので雑誌の方でも楽しみに読んでるんですが、作者さんの
解説通りなら、残り2冊分 (全15話) ってことなので、もうすぐ終わりそうなのは残念です。ただ、連載の方は10話まで進んで
ますけど、まだ着地点は見えて来ないですね。どんな結末になるんでしょうか。
―― 氷の国の王子様 第1巻 (了)
画像の著作権は全て著作権者に帰属します : © Haruka Ono 2012