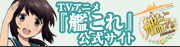ソ・ラ・ノ・ヲ・ト 第十二話 「蒼穹ニ響ケ」

「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」 第12話、最終回です。
初見のときは正直 「?」 だったのですが、何度か視聴してやっと頭の中で整理がついてきました。

最後まで視聴してみて。ちょっと自分の中で世界設定を壮大に捉えすぎていたのかなぁという風には感じています。
この世界は大昔に 「あいつら」 とやらに負けたことで、人類滅亡の危機に立たされているかのように語られてます。
海洋生物が絶滅していたり、ヘルベチア西部国境の向こうに 「世界の果て」 (no man's land)が広がっていたりと、
世界の危機的な状況を裏付けるような描写も数多く見られました。
しかし、結果的に人類の危機的状況にはほとんど改善も改悪も見られることなく物語は終了してしまいました。

そしてこの物語の根幹に存在している 「炎の乙女」 の言い伝え。
一話の頃から1121小隊は 「西の果て」、「砦の乙女」、「巨大な蜘蛛」 など、「炎の乙女」 の言い伝えに準えているような
部分があったので、言い伝えに似せた行動を取って結末を迎えるであろうことは予想していました。
タケミカヅチを駆った1121小隊が、「羽の生えた悪魔」 のような強大な敵と戦って世界を救ったりするのかな、と。
しかし最後になって、言い伝えそのものが間違っていたと言う展開で全てが覆ります。
炎の乙女は 「羽の生えた悪魔」 から 「街」 を守ったのではなく、「自分たちを滅ぼす筈のもの」 の 「命」 を守ったのだと。

そしてカナタたちも敵兵である筈のアーイシャの 「命を守る」 選択を取ることで、結果的には言い伝えの通りとなります。
さらにカナタが金の角笛で鳴らした 「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」 で、一時的にしろ両軍の進行を止めることも出来ました。
ただ、「羽の生えた悪魔」 との戦いによって人類滅亡の危機が迫っているという壮大なファンタジーから始まった物語が、
ハト派の大公に痺れを切らしたタカ派の大佐が、独断専行して戦争に持ち込もうとするところを、大公の娘が人身御供に
なって講和を成立させるという、結果的には随分リアリズムの範疇に収まっちゃったなぁ…という印象です。

それに、やはり説明不足と言うかご都合主義的な部分はあるように感じます。
公女を人質として皇帝に輿入れさせることで同盟を結び、講和を成立させる流れになるのは納得出来るんですが、
その人質(リオ)を1121小隊に返しちゃったら、輿入れすること自体に意味が無くなってしまう気がします。
それに人質にも使わない公女を娶っただけで休戦するくらいなら、そもそも講和会議が難航することも無いと思います。
まさか三人目の嫁欲しさに、皇帝が駄々をこねてたわけでも無いでしょうし、ローマの皇帝もヘルベチアの大公も、
どちらかと言うと戦争には否定的だったようなので、じゃあ一体何のために戦争してたんだろう?と言う疑問も出て来ます。

まぁ、本当はあまりこまい事を考えないで視聴した方が楽しめそうなアニメなので、世界の終わりだとか戦争だとかの要素
を省いて、もっとキャラクターに特化した作りにした方が良かったかなぁ?というところに落ち着きそうな気はします。

でも張り巡らされた伏線とか妄想するのは好きなので、一話から通して考えれば十分楽しめたんじゃないかと思います。
―― 第十二話 「蒼穹ニ響ケ」 (了)
「ソ・ラ・ノ・ヲ・ト」 の画像の著作権は全て著作権者に帰属します : © Paradores・Aniplex/第1121小隊
【関連記事】 ソ・ラ・ノ・ヲ・ト 第十一話 「来訪者・燃ユル雪原」
ソ・ラ・ノ・ヲ・ト
近況
| copyright © 2009-2018 月 奏 | |